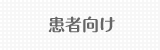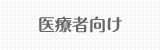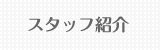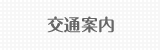医療者向けTOP
■ ご挨拶
| 徳島大学大学院医歯薬学研究部 臨床神経科学分野 教授 和泉唯信 |

脳神経内科の魅力
私は1995年(平成7年)に徳島大学医学部を卒業しました。当時は卒業時に自分の進む診療科を決めるのが慣例であり、私は脳神経内科にしました。なぜ脳神経内科を専攻したのかを振り返ってみましょう。まず内科、外科で分けた時、内科の診療科に決めました。内科の中では循環器内科、血液内科、脳神経内科を候補にしたのですが、当時の徳島大学医学部生化学教室教授山本尚三先生の「和泉君は脳神経内科がいいよ」というひとことで脳神経内科にしたわけです。生化学に興味を持ち教室によく行っていた私には、将来生化学的アプローチが重要になってくる脳神経内科が合っていると山本先生は思われたのではないでしょうか。それから27年経過しましたが選んで本当に良かったと思います。
それなりに脳神経内科医としての経験を積んだ私の考える脳神経内科の魅力はたくさんあります。今回は、そのうちの3つを取り上げてみたいと思います。1つは検査よりも医師の診察が重要な診療科であること、2つ目に、対象となる疾患が多彩であること、そして、現在進行形で治療法が進歩しつつある領域であること、です。
まず診察の重要性ですが、神経学的所見として意識レベル、高次脳機能、脳神経、運動、反射、協調運動、感覚、起立・歩行、自律神経を確認し病変部位の推測をします。もちろんその後に画像検査や神経生理学的検査を行うわけですが、なんといっても問診・病歴聴取と神経学的診察が重要です。この神経学的診察は身につけるのに一定期間の修練は要りますが、一度修得すればどんな場所でも実力を発揮することができます。それに対して、がんなどの生検で確定診断ができる疾患は、その生検すべき部位をより早く描出することが重要です。いきおい患者さんは病変を描出できる「機器」をめがけて受診するわけです。一方脳神経内科疾患では、その病変をいち早く正確に確認できる「医師」をめがけて、患者さんは受診することになります。なぜなら、医師が病歴と神経学的所見から病変の性質と部位を推定し、それをふまえて検査方法を考えて決めるからです。このように病変を想定し診断していくのが醍醐味です。この背景には、「機能局在」という脳・神経系特有の性質があります。検査技術や機器はこれからも進歩していきます。それでも脳神経内科においては、神経学的診察という人の手による「手技」がこれからも重要であり続けるでしょう。その点が私の感じる脳神経内科の魅力の1つ目です。
次に、疾患が多彩であることです。脳、脊髄、末梢神経、神経筋接合部、筋のどこに病変があっても病気になりうるのでその疾患は多彩です。その中で特に患者数が多いのが認知症、脳血管障害・脳卒中、頭痛、てんかんです。いまだに、認知症は精神科、脳卒中や頭痛は脳神経外科、てんかんは小児科だけが診療していると誤解されていることが多いのです。もちろん各診療科と協力して診療にあたる必要がありますが、これらは脳神経内科がプライマリーに診るべき疾患です。これら4疾患にはそれぞれ専門医があり、それらを深めていくことも可能です。また、2017年から新しい難病制度が始まり、現在340以上の疾患がその対象になっていますが、脳神経疾患はその中の最多を占めています。難病対応も重要な取り組みであり、それを専門にしている脳神経内科医も少なくありません。
3つ目の魅力は現在進行形で治療法が進歩していることです。私が研修医だった頃は認知症の治療薬はありませんでした。現在は認知症の代表的な疾患であるアルツハイマー病においてその脳内で蓄積するアミロイドβを除去する薬剤の国内での承認が期待されています。脳血管障害も以前は発症直後に受診してもほとんどが後遺症を残す状況だったのですが、抗血栓療法と血管内治療の進歩によって機能予後が著しく改善しています。片頭痛やてんかんも有効な薬剤が発売され患者さんのQOLを向上させています。難病の治療も進歩しています。特に免疫性疾患である重症筋無力症、多発性硬化症、視神経脊髄炎スペクトラムの治療は著しく進歩しました。徳島大学脳神経内科では、有効な治療法のない筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療法開発に取り組んでいます。2022年には高用量メチルコバラミンが発症早期のALS患者に有効であることをJAMA Neurologyに報告し、現在企業が承認申請の準備を進めています。以前は治療効果が十分でなかったり、診断をつけるだけで終わっていた状況が相当に改善されているのを年々肌で感じています。また、地方大学からでも成果を挙げることが可能です。それが現在の脳神経内科の大きな魅力の一つです。
今回、脳神経内科の魅力を3つ挙げさせてもらいました。学生・研修医の皆さん、このような魅力がありどんな場所でも力を発揮できる脳神経内科で一緒に取り組んでみませんか。
2023年(令和5年)2月1日
学歴
1983年3月 広島県立日彰館高等学校卒業
1989年3月 北海道大学理学部数学科卒業
1995年3月 徳島大学医学部医学科卒業
2001年3月 広島大学大学院医学研究科博士課程修了
職歴
1995年4月 広島大学医学部附属病院研修医
1996年1月 翠清会梶川病院脳神経外科研修医
1996年4月 財団法人住友病院神経内科医員
1998年8月 微風会ビハーラ花の里病院神経内科医員
2001年4月 徳島大学医学部附属病院医員
2001年7月 徳島大学医学部助手(難聴診療部)
2004年1月 徳島大学医学部講師(神経内科講座)
2008年4月 医療法人微風会理事長、社会福祉法人慈照会理事長
徳島大学病院診療支援医師、徳島大学医学部非常勤講師
2018年4月 徳島大学病院特任講師(神経内科)
2020年2月 徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床神経科学分野(神経内科)教授
所属学会
日本内科学会(認定医)、日本神経学会(専門医、代議員)、
日本老年医学会(専門医、代議員)、日本神経治療学会(評議員)、
日本認知症学会(専門医、代議員)、日本脳卒中学会(専門医、代議員)、
日本老年精神医学会(専門医)、日本頭痛学会(専門医)、
日本早期認知症学会(理事)、日本認知症予防学会(評議員)、
日本心血管脳卒中学会(学術評議員)、日本神経生理学会(代議員)、
日本神経病理学会(代議員)、日本神経超音波学会、
日本パーキンソン病・運動障害疾患学会、日本自律神経学会、
日本正常圧水頭症学会、日本ニューロリハビリテーション学会、
American Society of Human Genetics